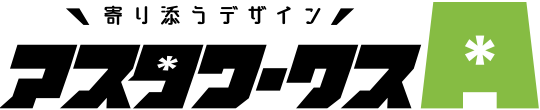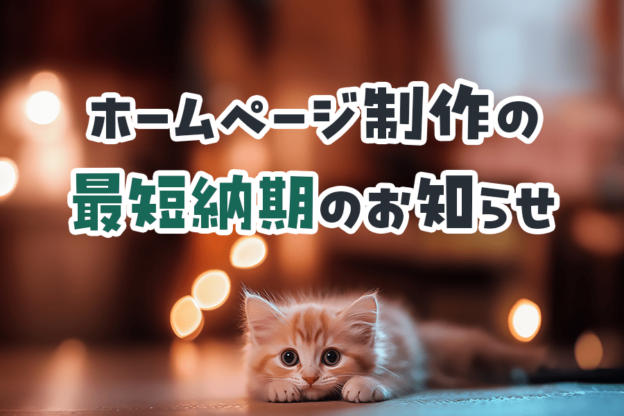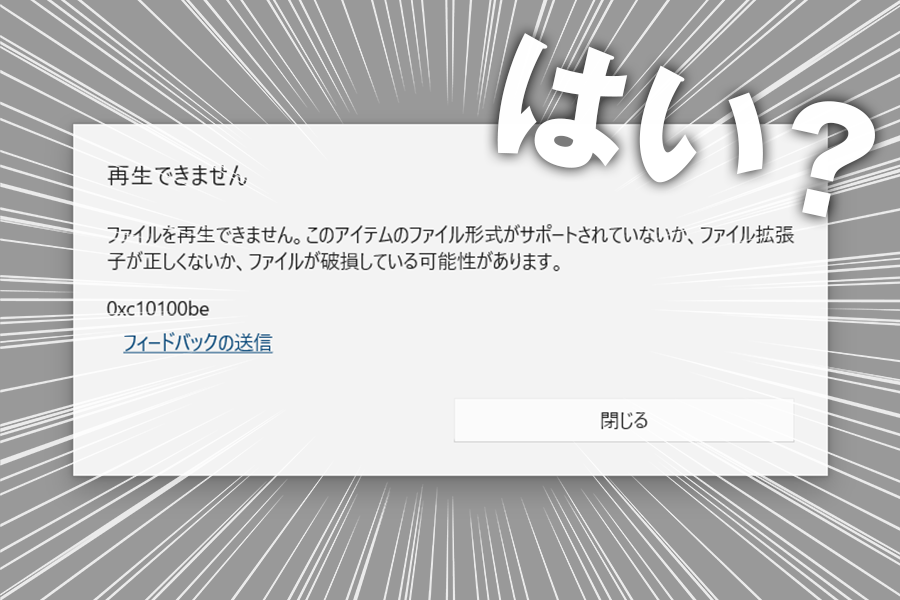お世話になっております。
アスタワークス原田です。
2023年10月より開始されたクソインボイス制度について、当事務所の基本方針をお知らせします。
当事務所は免税事業者です。
当面、課税事業者登録をする予定はございません。
当方に適格請求書の発行資格が無いため、恐れ入りますがインボイス制度開始後は、実質的※に10%(経過措置期間は2%~5%)の値上げとなります。
とはいえ、アスタワークスといたしましては、これまで同様、市場の相場感と当方の提供可能価値を鑑み、比較的割安感を損なわないよう善処していく意向でおります。
都度見積もり額にて、増加コストを鑑みたうえで適宜発注をご判断ください。
今後については、市場状況に応じ、取るべき方針を検討予定です。
ひとまず経過措置3年の間は課税事業者登録を行わない方針とさせていただきます。
経過期間中は、特例の仕入れ税額控除を受けていただくため、ご請求書に区分記載による消費税記載を行います。